前回は本書の前半、ガラパゴスへ向かうまでについて感じたことを書いた。いよいよ本編。生物学的な書き出しというより、冒険記っぽい書き出し。
まずは乗船する船、そして旅をサポートするチームメンバーについて紹介される。学術的な記述に一気に入り込むより、逆にわくわく感が高まる。
船のトイレ事情と「ピシュス(自然)」については、読者としても想像力豊かにその狭い個室と衛生状態を身近な自分ごとで捉えることができた。加え、船の全体構造、こじんまりとした居住空間や、船長、ネイチャーガイド、同行カメラマンのそれぞれの立ち位置。そしてシェフと創られる料理の数々。否が応でもガラパゴスへの旅に読者としても期待感が盛り上がる。ただこの商業的に万全の準備が施されているこの旅を作者はなんとカテゴリーするのだろう。“冒険“ “旅“ それとも“取材旅行“。
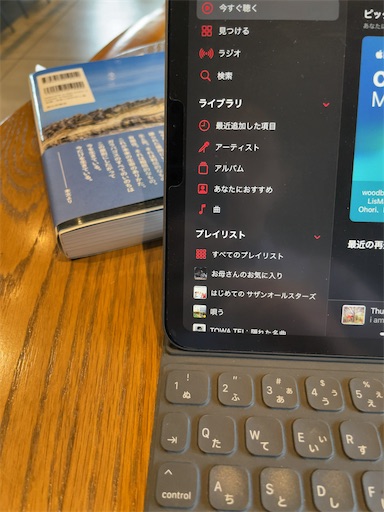
何よりも記憶に残る記述は「ガラパゴス諸島は、決して世界から取り残されてしまった場所ではない。むしろ、世界最先端の、進化の前線」と言う一節。
ガラパゴスはガラケーに代表されるように古く取り残されたイメージの代名詞となっているが、著者は落ち着いて否定する。これが現地を旅した人だけが得られる感覚かと言ういうと、そうでもない。読み終えた頃にはその言わんとする事が理解できる。
ガラパゴスほどでない、身近な旅に出たい。改めて感じた。
